

Profile
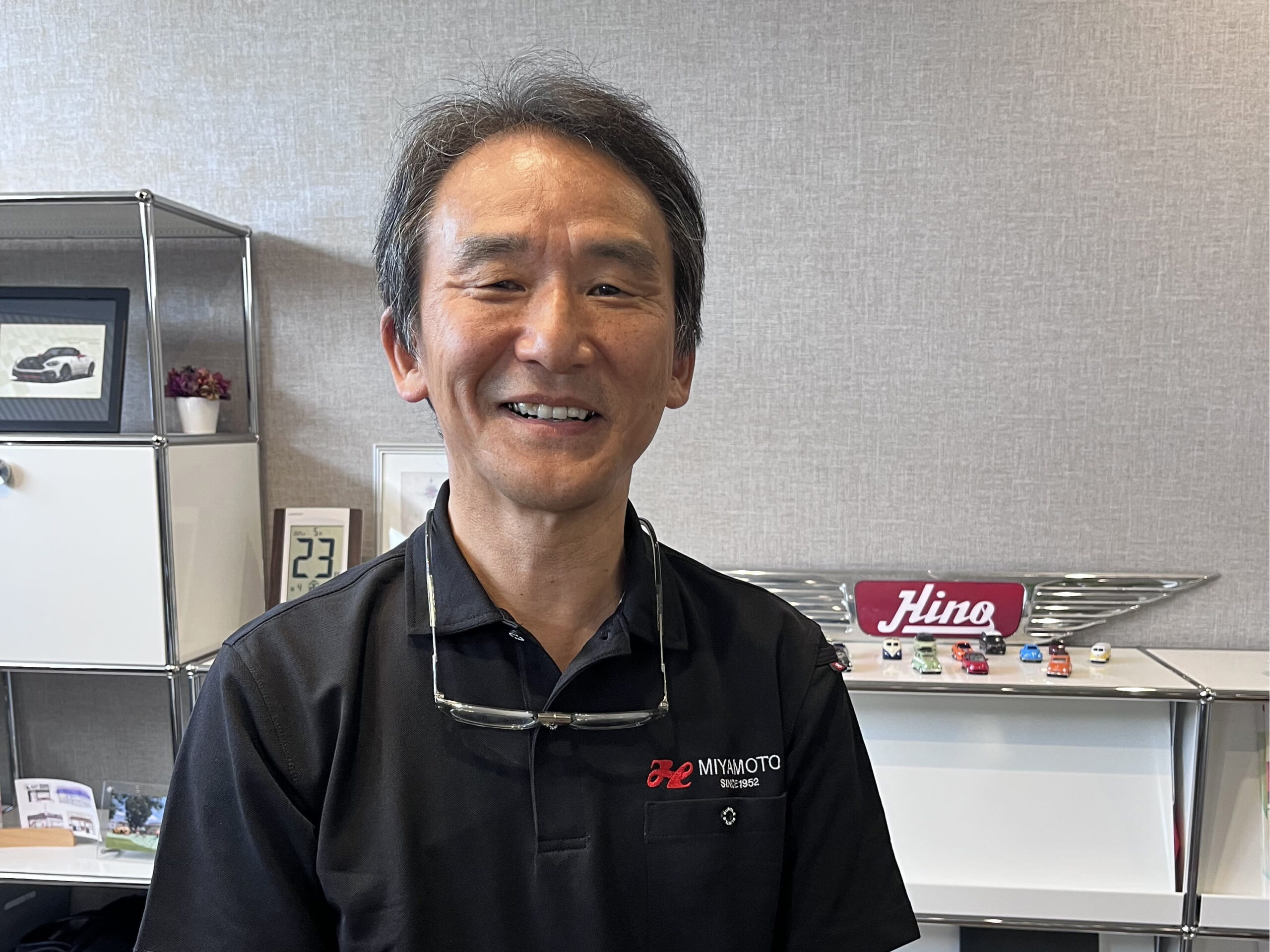
大阪東ブロック 京阪支部 1991年度入会
株式会社ミヤモト 代表取締役社長
宮本 眞希
所在地:大阪府門真市岸和田1-2-8 /
URL:https://www.miyamoto-truck.co.jp
創 業:1952年 / 設 立:1964年 /
年 商:18億円(関連会社含む・2024年度) /
社員数:正社員36名 パート9名
事業内容:新車、中古トラック、純正部品、リサイクル部品、環境機器の販売、トラックボディの製作
トラックビジネスに特化した企業
株式会社ミヤモト(以下「(株)ミヤモト」)は1952年に宮本さんのお父様が、米軍の払い下げのトラックなどを買い取り中古部品の販売業として創業しました。
その後、大手トラックメーカーの販社である現在の大阪 日野自動車株式会社と取引が始まり、1964年に株式会社 宮本商店を設立しました。その後大手トラックメーカー4社 すべてと取引を行い、会社は大きく発展し続けています。

時代の流れで大きく変わるトラック業界
20年前は乗用車も含めた4輪車の新車販売台数は約800 万台でしたが、現在の販売台数は約500万台です。その中 でトラック(4トン以上)の販売台数は10万台、2トント ラックを含めても30万台と非常にニッチな業界です。コロ ナ禍やリーマン・ショックの時は半分の5万台にまで落ち込ん だとのことです。景気に大きく影響を受ける業界といえます。
トラックを扱う運送業も大きく変化しています。免許制 度の問題では若い人が2トントラックに乗ることができませ ん。2024年から始まった運送業界の働き方改革で運ぶ人 がいないというような状況になっており、運送業界の廃 業、倒産が増加傾向にあり、ビジネス環境はますます不安 定化しています。
4大トラックメーカーもこの状況に対応するために、大き く統廃合が起ころうとしているようです。その流れのなか には海外メーカーのダイムラーやボルボなどもあり、この 先数年でメ ーカーは大きく変わると予想しています。
ちなみに、海外のメーカーは、昔から大陸を走ることを 前提としてつくられてきたので、トラックとしては非常に 性能がよく、日本メーカーでも勝てないとのことです。
時代の変化に対応
宮本さんは他社での経験を経て、1990年に(株)ミヤ モトへ入社しました。その頃はバブル景気で日本全体が元 気な時代でした。トラックの販売も一人で月50台売った り、1本の電話で30台の注文があったりと非常に好景気な 時代でした。
(株)ミヤモトに入社後、バブル崩壊にもあいましたが、それまでの堅実な経営のおかげでそれほどの落ち込みは なかったようです。その頃の業態はトラックの新車、中古 車の販売、部品パーツの販売、中古部品の販売をメインに していました。
2000年以降は車輌の安全・環境対策、そして物流改革 やドライバー不足などさまざまな問題でトラックの買い替え需要低成長時代となりました。
このような外部環境の変化への対応として、車輌メンテ ナンス事業の充実に着手しました。認証工場から国土交通 省指定工場へとランクアップし、国に代わって車輌車検業 務ができる整備工場、そして車輌の改造や塗装などお客様 のご要望にお応えできる体制を整えました。
中古部品を共有する協会に参画
中古部品の生産・販売は車輌入れ替え需要が大きく影響 します。低成長時代では車輌の確保が難しくなってきていました。中古部品在庫の充実は一社では限界があります。
当時全国の中古部品業界では少しずつ在庫共有化の動き があり、全国の同業50社の仲間たちと、中古部品の共有在 庫を行う「日本トラックリファインパーツ協会」に参画しました。
協会への参画の話をした時は、古参の社員からは「ミヤ モトの在庫はミヤモトの物、情報をオープンにするのは手 の内を見せることになる」と反対の声が上がりました。し かし、宮本さんは今後の業界の状況を考え、協会への参画 を決行しました。
(株)ミヤモトはトラックだけを専門に取り扱っていますが、これは大阪という都市だからできることであり、地 方の協会員はトラックだけでは経営が成り立ちません。地 方は乗用車も扱うなど、いろいろと工夫をしなければ生き 残れません。そのような地方の協会員の経営を見ることで 勉強になったとのことです。
「この地域はミヤモトに」
近年トラックも高度化された車になっています。高度化 された現在では情報やデータが無いと修理ができません。 ディーラーと対等にうまく付き合っていくことが今後の大 きな課題になっています。
メーカーの代理店としての位置付けも変化してきまし た。販売数量はもちろん、組織力・設備・技術力、そして 人材教育ができているかなど、基準が非常にシビアになっ てきました。メーカーから「この地域はミヤモトに」と任 せていただけることが今後の重要課題になってきました。
また、(株)ミヤモトの部品販売先である地域の整備工 場は車輌の技術革新や作業員不足、そして後継者問題で厳 しい状況になっています。時代と共に変化する市場を正確 に分析して、(株)ミヤモトも時代と共に変化が必要! と、宮本さんはまだまだ模索中です。
次の世代へ
宮本さんは50才過ぎまで外に出っぱなしで走り回るよう に仕事をしていました。ふと社内を見ると、社員たちの方 向がバラバラで社内教育ができていなかったことを痛感し ました。それからは社内整備に力を入れるようにしています。しかし、自分が先頭に立って指揮をとるのではなく、 次世代の若い社員を主体に社内整備を推進するようにして います。自分が先頭に立てば古い成功体験が邪魔になると の思い、また社員たちの頭の回転の速さなどを感じていま す。顧客や業界の方たちが若返ってきており、若い世代の ネットワークができてきていることも感じています。
現在は、息子さんと娘さんが会社に入っており、次世代 へのバトンタッチもそろそろのような話でした。

リトル、イノベーション
2022年に(株)ミヤモトは70周年を迎えました。それ に向けて会社で70年間続けることができた理由(何が良 かったのか?これから今までやってきたことが通用するの か?これから何をしていくのか?)を社内で議論しまし た。
そうすると、まだまだできていないことがたくさんある ことに気づきました。そこで生まれた言葉が「リトル、イ ノベーション」。小さな改革です。これを合言葉として (株)ミヤモトは変わり続けていきます。

(取材:大西・山田/文:山田/写真:山田)
同友会 私の楽しみ方
同友会には経営を学ぶツールがたくさんあります。有益な情報を得て も、結局やるかどうか決めるのは自分、実践するのも自分です。例会で経営 体験を聞いてそれを取り入れても、うまくいきません。まずは自分の会社 に合うように変えてみて、実践する。しかし、それでもうまくいかないこと ばかりです。それでも実践し続けることが大事だと思います。
1991年入会で会歴は35年になりますが、昔、先輩会員から多くのこ とを教わりました。印象的に覚えているのは「『居てほしい人』より『居なく ては困る人』になれ」です。そんなことを教えてくれる経営者に多く出会う ことが大事だと思います。



